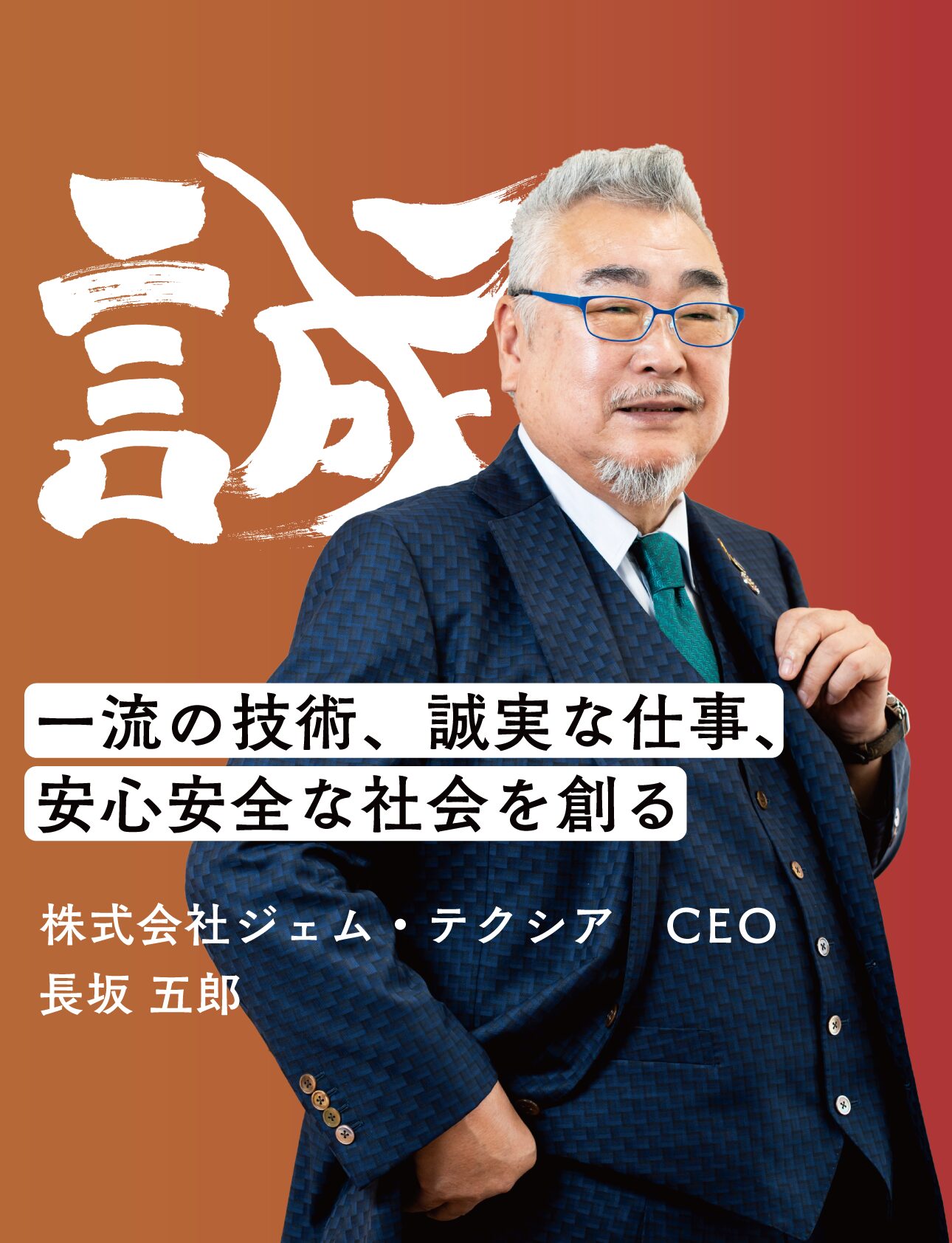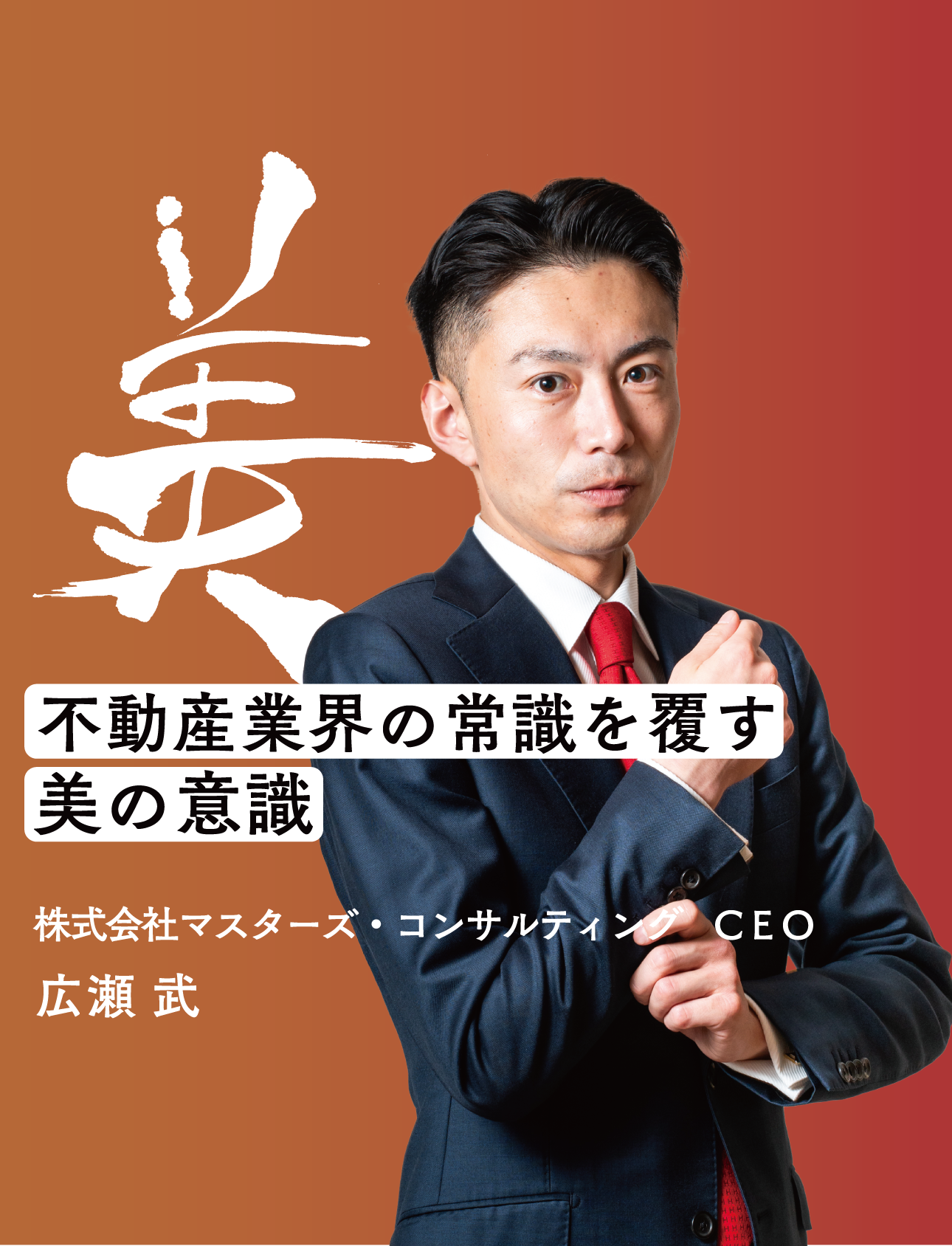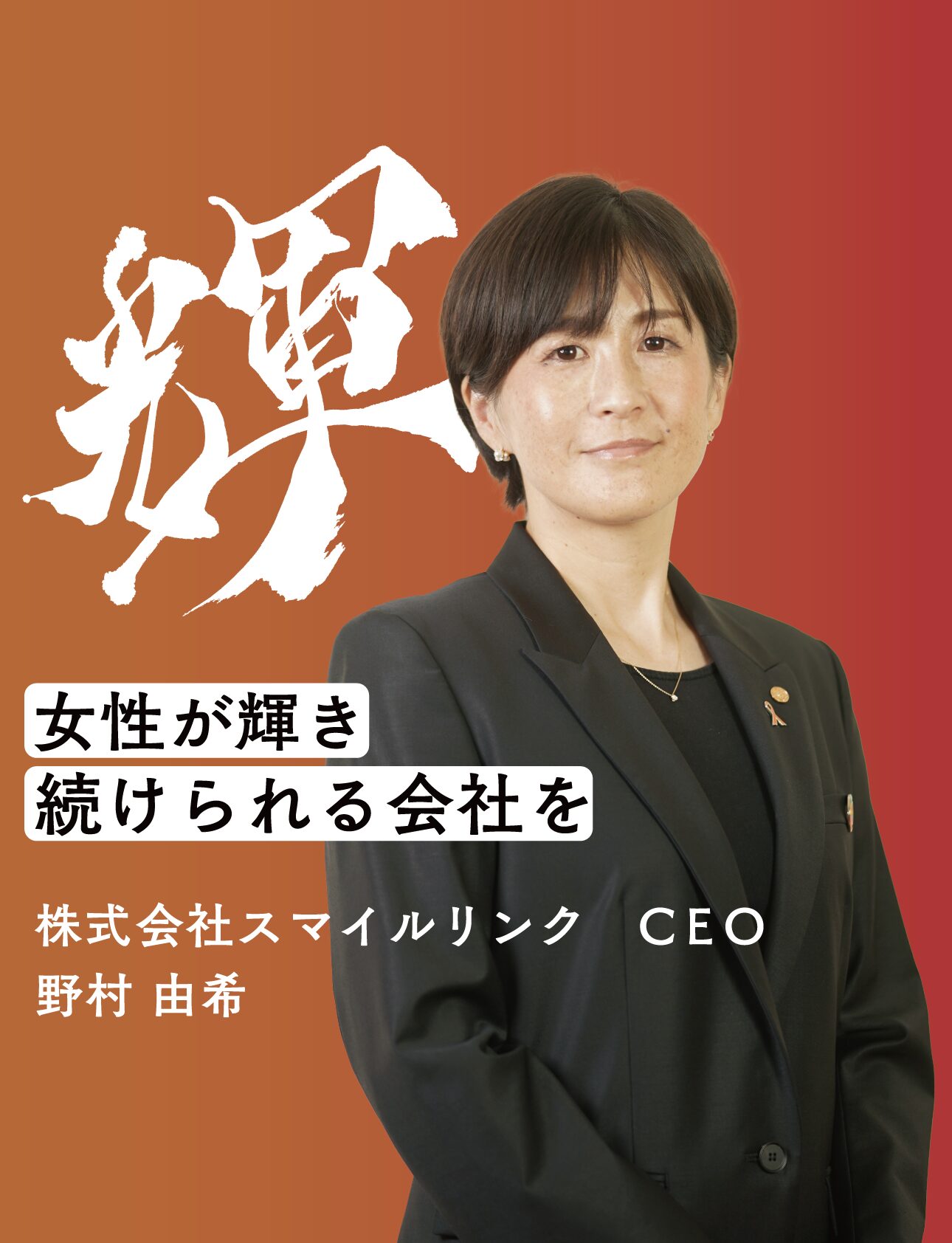株式会社NARITAYA 代表取締役成田 禎仁違和感に挑み続ける、
株式会社NARITAYA 代表取締役 成田 禎仁社長の挑に迫る。

NARITAYAに込めた想い
志を漢字一字で表すと、「挑戦」の「挑」です。
2年前に13年経営してきた会社を売却して、今の日本酒バーをはじめました。前職は、電気工事業や通信工事業、IT業、業務改善のコンサルティングなどを事業としており、仙台・盛岡・弘前への出張の際に酒造に赴き、美味しいお酒を楽しんでいました。実は、その延長線で日本酒を事業にしただけで、正直なところ何か使命を感じて始めたわけではありません。
この話をすると、周りから「安定していたのに、もったいない」とおっしゃる方もいましたが、このまま安定した生活を送るのはなんだか物足りなく感じていました。
もちろん、事業がうまく行かないかもしれないという不安はつきまといます。しかし、私は仕事も人生も全て、挑戦して切り開いていくというのをモットーとしていますので、「挑」の字にしました。
ここで言う挑戦とは、メラメラと赤く橙色に燃えている炎のイメージです。丸よりも角のある金平糖のような形で、触ると熱いと感じる、まさしく私の心を表しています。
まさに株式会社NARITAYAもチャレンジの一つとして立ち上げました。自ら現場に入って一人で全ての仕事をするという原点に戻ってやり遂げられるかというチャレンジです。前の会社では従業員を30人ほど抱えていたため、社長としての仕事に専念すればいいのですが、一人でやるとなるとそうはいきません。今の自分は一人で仕事をして事業を大きくする能力が備わっているのかわかりませんが、苦しいからといって従業員を雇うようなことはしません。あくまでも一人で挑戦していくということです。
また、サラリーマンも個人事業主も、自分のポテンシャルを信じていない方も多いのではないでしょうか?
この挑戦を通して、働き手の皆が持っている目標をどのような手段で達成していくのかを見せることで、新しい価値観を提供したいと思っています。
例えば、私は今までITの会社を経営していましたが、日本酒バーの業界は初めてです。なぜ日本酒バーなのかというと、単純に私自身が日本酒に詳しく楽しそうだからといった理由です。楽しそうと思わなければ、やりがいを感じないですし、なかなか困難な業界だからこそ好奇心が持続してやっていけると思いました。私は低い山を登ろうと思わないタイプで、常に好奇心を掻き立てるのに日本酒の山が高くてちょうどよかったと思います。
私が27歳の時、「今思いついたことはもう既に古いんだ」という尊敬する70代の人生の先輩からいただいた言葉が私の価値観の原点になっています。今思いついてその課題に取り掛かったらもうそれは古いからすぐ次に取り掛かろう!常に物事を良くしていくことに向かっていくという好奇心、探究心が大切だということです。それが私の挑戦のかたち、根幹で常に忘れないようにしています。
自分が挑みたいことを常に見つけていく姿勢で志事をしていきたいと思っています。

業界で違和感を覚えたところ
ただ、実際にこの業界に入ってみて、違和感を覚えるところも正直いくつかあります。
一つ例を挙げるならば、伝票の処理方法です。データ入力したものを印刷して郵送し、それを受け取った人が手作業でデータをパソコンに入力するといった、二度手間があたりまえのように行われています。私の店の場合、200種類の品目があり、それをどの品目が売れたのかを確認し、一つ一つ手で入力するのは、なかなか大変な作業です。おそらく多くの日本酒メーカーや店舗で無駄なことが行われていることでしょう。
そもそも、伝票のデジタルデータを入れるのは酒屋の仕事なのでしょうか?
酒造メーカーはお酒を作ることが仕事なので、できる限りそこに注力していきたいところです。そのため、デジタルデータをアナログに変換して、またデジタルデータにする、ITに携わっている私からすれば「無駄」でしかありません。お酒を提供しながら、例えば在庫管理のシステムはこれを入れるとか、私がIT化を推進していくことでそのメリットを見せていきたいです。より質の良いお酒が出来上がったり、さらに品揃えを充実させたりできれば、注目してくれることかと思います。
確かに、業界の慣習が根付いているため、なかなか改革を起こすのは難しいですが、ITも上手に駆使していくといった価値観に変えていきたいところです。

未経験者が業界に挑戦していくには
人間関係が大事!
まず、変革をしていくには、私は新参者なので、やはり人間関係を作ることが大事です。
そこで、時間があれば酒造メーカーに足を運び、会話をするようにしています。会話を通じて、相手の悩みを聞き出そうと思っていますが、まだまだ十分ではなく、今そこが私の課題かと思っています。
特に、ITを導入する良さを上手く伝えきれていないのが現状です。
そこで、IT導入の話が刺さるかどうかではなく、実際に成果を見てもらおうとも思っています。例えば、在庫管理をしていく中で、ここに測り重量計のシステムを入れれば、日本酒の瓶内の重量を測るだけでより正確な在庫管理ができます。
さらに、どのお酒がよく出ていて、どのお酒が出ていないのかがデータで現れるので、そのデータを共有した上で「新酒をやめて既存のものに変えましょう」などの提案もしやすくなるでしょう。これによって、「なぜ既存のものに変えるのか」を口頭で説明する時間が省け、もう一歩進んでコミュニケーションを取ることができます。先方の問題を早く感知して、解決に持っていくこともできるでしょう。
歴史のある業界の中に新しい価値観を提案していく、これこそ私の挑戦です。

日本酒選定で欠かせない3つのこだわり
また、お酒を多く飲んでもらう人を多く作るとか、紹介するというより、お酒を飲めるところに日本酒を入れているくらいの感覚なので、イベントを開いてお客様を取り込むことはしていません。
今、私のバーで取り扱っている日本酒は178銘柄です。ただ美味しいから取り入れているのではなく、実際に酒造に赴いて会話をして、3つの選定条件をクリアーしているかを判断した上で取り入れています。
・米作りに関与しているかどうか
・県内産の米を使っているかどうか
・酒造りにポリシーがあるかどうか
美味しいのは絶対条件で省いていますが、なぜこのような条件を作ったかと言いますと、バーでお客様からいただいたお金をクライアントの酒造さんに還元したいと思っているからです。
お酒を作るにはお米を作る必要があり、お酒用の田んぼを作り、いいお米を作ろうとしている農家の存在が欠かせません。お酒を作ることで農家の給料となるため、そこに酒造が着目しているかが気になります。極端な話、1000km離れた田んぼの美味しくて有名な米を使って酒造りをするより、2kmほど離れた田んぼのお米で美味しいお酒を作ろうという探究心を持ってもらいたいとも思っています。
地域の田んぼのお米を使うことで、一次産業を支え、地域雇用が新たに生まれ、地域貢献に繋がるなどといった、お酒を作るポリシーが色濃く出るところです。そういう心意気のある酒造を大事にしたいのです。

お客様の好みを見つけて
喜ばれることがやりがい
私のバーには、もちろん日本酒が好きなお客様も多いですが、中には日本酒を飲み慣れていない人もいらっしゃいます。日本酒は種類も多いですし、ボジョレヌーヴォーのように年によって味も変わってきますので、中には日本酒はとっつきにくいなと感じている人もいるでしょう。
日本酒を飲み慣れていない人が自分の日本酒の好みを見つけて、その美味しさに感動された姿を見ると、私はこの仕事をやっていてよかったなと、やりがいを感じます。「美味しいからまた飲みたい」と店頭で日本酒を購入して帰られたお客様もたくさんいました。
また、お酒を飲む人でも意外と自分の好みがわかっていないようで、「自分は辛口が好き」と思っていても、実はフルーティーな甘めのものがその人に合っていたりします。カウンターに立って、お客様一人一人と会話をしていくうちに、そのお客様が本当はどのようなお酒を好きなのかがわかるようになってきました。
つまり、私の日本酒バーはお客様が好みのお酒との出会える場所だと考えてもらいたいです。先程お話しした通り、私自らお酒を選んでいるため、酒造メーカーの方でさえも知らないお酒が置いてあったり、メジャーなお酒が置いていなかったりします。高額なお酒がいいものとは限らず、安価なお酒の方が好みに近い時もあります。
お客様もいつも飲んでいるお酒ではなく、たまには新しいお酒を飲もうという気持ちになることはありますが、常連の方はいつも同じお酒を飲まれるケースが多いようです。自分の好みのものがわかれば、飲み続けていたいということでしょう。

私がキャッシュレス化にこだわるわけ
いくつもの事業を進めると、いかに時間をどう振り分けていくかが課題になっています。酒屋の仕事をしていると、昼間の仕事に時間を使えなくなります。どう振り分けていくと効率的で成果が出るのか、それを今、模索している段階です。
また、私の場合、お金をいかに稼いでいくかというより、キャッシュレス化の推進にとことんこだわっています。北海道日本ハムファイターズの本拠地であるエスコンフィールドよりも先にキャッシュレスを導入しています。おそらく私のバーが札幌市内で一番早く導入したのではないでしょうか?
多くの飲食店や酒屋など、現金払いで日銭を得ることを望んでいるかと思いますが、私は現金にこだわるあまり、お金の管理やお釣りを用意することなどの準備に時間を費やしたくないのです。
そういうところに力を入れるより、蔵元をめぐって色々なお酒の情報を得る方を優先したいと考えています。豊富な情報量があるからこそ、なかなか手に入らないレアなお酒を買い付けできるのです。
そのためには、その蔵のある土地の情景に気づくことが大事です。その土地で遊んだり、ご飯を食べたりすることでわかることも確かにあります。つまり、その土地の魅力や作り手としての蔵元の情熱に触れることで、その土地の情景が見えてくることがあるので、その土地の情景を伝えて行きたいと思っているのです。
余談ですが、私はムーミンに出てくるスナフキンに憧れていますが、今していることはスナフキンと変わらないかもしれません(笑)。

蔵元のプラットホームを!
世の中には、まだまだ日本酒に対する誤解があると感じます。味噌や醤油などの調味料が製造過程の中で酵母や麹を使われていることを知らない方もいらっしゃいます。お酒というものは思っている以上に身近なものなのです。お酒は飲兵衛だけのものなどというふうに思ってほしくないのです。
そこで、多くの人にお酒を生活の中に入れていただき、好みのお酒を嗜んで5分でもその美味しさに浸る時間があってもいいのではないかと思います。
そのため、これからの販売手段ですが、いかにお客様の生活ルーティンの中にお酒を入れていくかだと考えています。
そこで一つのパイプになると感じたのは、蔵元の考え方のプラットホームです。
私はアンバサダーという形ではなく、お客様にそれぞれの蔵元が大事にしている考え方のプラットホームを紹介していくといったことをしていきたいです。考え方のプラットホームをお客様が理解してくれれば、その蔵元を応援したいと思うでしょう。地域がうまく循環するように思うのです。
しかし、今、お付き合いのある蔵元のポリシーですら、なかなかお客様に伝わっていません。
もちろん、お客様に伝える前に私自身が蔵元のプラットホームを十分に理解していないとならず、まだ数者くらいしか真に迫った話を聞き出せていない状況です。
200年以上も積み上げてきた蔵もありますし、1年や2年の人間関係で聞き出せるとは私は思っていません。それこそ時間がかかることですし、伝統のある蔵元といかに人間関係を築いていくかが当面の私の課題と言えるでしょう。


私が今回紹介する愛テムは、最新のスマートフォンと浄法寺の漆を塗ったボールペンです。筐体はトンボ505シリーズを基にしたもので、150年の歴史を持つトンボが外部に初めて設計図を出した代物です。
きっかけは、盛岡の文房具店の一言から始まったそうです。漆職人が減っており、漆職人を目指す若者を増やしたいということで、漆のボールペンが生まれました。
私は職業を選ぶ際に、「その職業は憧れられるか」が大事だと思っています。実際にこのボールペンを手に取ってみて、デザインといい、質感といい、かっこいいと思いました。漆に触れてみて、こんなかっこいいものを作る職人になりたいと思う人も増えてくるのではないでしょうか。私は意外に思うかもしれませんが、文房具が好きであり、こういう作り手の思いがのったアナログなものが好きです。
また、私が尊敬する営業マンが言っていた言葉から、ものを通じて思いを届けることの大事さも感じました。
当時、23歳だったその営業マンから購入したいということで、契約書にサインをすることになった時、エンブレムを見せながらモンブランのボールペンを渡してくれました。お客様に取って数百万円もする大事なお買い物に対して、それ相応のボールペンを用意しないとお客様に失礼とおっしゃっていたのです。
この一件で、高級なボールペンを使うからこそ価値があるというのではなく、私は相手への配慮として気の利いたアイテムを使うことの大事さを学びました。それ以来、お店のレジのところでクレジットカードでお支払いした際のサインを書いてもらうとき、百均にあるような安いペンを使うなよと注意するようにしています。
ボールペンとスマートフォンはアナログとデジタルで対局的なアイテムですが、利益を上げるためには効率の良い仕事も大事だと思っているので、そちらはデジタルで、デジタルでないところの側面はこのボールペンのように相手への気遣いとしていいアイテムを揃えることも非常に大事なことだと思っています。
Profile
- 株式会社NARITAYA
- 代表取締役 成田 禎仁
-
- 1968年12月
- 北海道釧路市生まれ
-
- 1989年3月
- 北海道立札幌高等技術専門学院(旧:職業訓練校)卒業
-
- 1989年4月
- 機械加工や金型製作の会社に勤務。製造業を10年間経験
-
- 2000年7月
- 友人数名と会社設立したが2年で失敗し単独で個人事業主で活動
-
- 2009年10月
- 株式会社シージェイシステム設立 資本金25万円
-
- 2021年10月
- Sake.bar.成田屋開業(飲食店)
-
- 2022年7月
- 株式会社シージェイシステムをM&Aにて売却 売却額1億2500万円
-
- 2023年10月
- 酒類小売業免許を取得しSake.成田屋に店名変更